
「職場の人間関係が辛くて転職したいけど、それってアリなの?」
「このまま耐えるべきか転職すべきか、判断できない」
職場での人間関係が悪いためにストレスが強くなってくると、転職が頭をよぎりますよね。その一方で、転職は「逃げ」のようで後ろめたい・何を基準に決断すべきかわからないという人も多いでしょう。
実際には、人間関係が理由で転職する人は少なくありません。下図からわかるように、人間関係が理由で転職したという人は2019年時点で男女ともに1割前後おり、その人数は増加傾向にあります。

参考:厚生労働省 雇用動向調査結果の概要(2011~2019年分)
また、強く慢性的なストレスは病気につながるため、そこに至る前に転職するというのは賢明な判断です。
ただし、転職は人間関係の万能薬ではありません。転職によって人間関係の悩みから解放されるケースがある一方で、転職先で新たな人間関係トラブルが起こることもあるのです。さらに、転職はキャリアに関わる重大なイベントなので、安易に決めるべきではありません。
そのため、人間関係を理由とした転職は、以下の4つのステップを踏んで慎重に検討すべきです。
 この記事では、以下について詳しく解説します。
この記事では、以下について詳しく解説します。
▼人間関係が理由で転職する人が増加している現状
▼人間関係を理由とした転職を安易に決めてはいけない理由
▼人間関係を理由とした転職をするか否か判断するための4つのステップ
▼転職先でよい人間関係を築くコツ
この記事を読むことで、人間関係が理由の転職ってどうなの?というモヤモヤ感が解消されるでしょう。なぜなら、人間関係を理由とした転職というものをどう捉えるべきかが理解でき、転職するか否かを判断するためにやるべきことが明らかになるからです。
職場での人間関係ストレスから解放されるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 人間関係が理由で転職する人は増えている

近年では、人間関係が理由で転職する人は少なくありません。また、その人数は増える傾向にあります。
以下は、転職者が前職を辞めた理由について、その割合を調査した結果です。

参考:厚生労働省 2019 年(令和元年)雇用動向調査結果の概況
前職を辞めた理由、すなわち転職理由について、内容が不明確な「その他」を除外すると「職場の人間関係が好ましくなかった」が男性では3番目・女性では1番目に多くなっています。
また以下は「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由で転職した人の割合を、経年的に示したグラフです。

参考:厚生労働省 雇用動向調査結果の概要(2011~2019年分)
2019年に人間関係が理由で転職した人の割合は男性9.3%、女性14.8%であり、調査が始まった2011年から現在まで、男女ともに増加傾向にあります。さらに、転職理由の中でこの「職場の人間関係が好ましくなかった」が、男女ともに前年と比較して最も上昇幅が大きかったそうです。
以上のことからわかるように、人間関係が理由で転職するというのは、珍しいことではないのです。
2. 人間関係を理由とした転職は安易に決めてはいけない

人間関係を理由とした転職は珍しいことではなく、人間関係をリセットするための特効薬でもあります。また、人間関係ストレスによって病気になることを避けるために転職するというのは、賢明な判断だといえます。
ただし、人間関係を理由とした転職にはリスクもあるため、安易に決めるべきではありません。
リスクとは「必ずしも効果が得られるとは限らない」こと「キャリアプランに影響する可能性がある」ことです。それぞれについて解説していきましょう。
2-1. 転職したからといって人間関係ストレスから解放されるとは限らない
まず押さえておきたいのは、転職は人間関係ストレスを解消するための万能薬ではないということです。転職で人間関係ストレスが激減したというケースがある一方で、転職先でも新たな人間関係ストレスを感じ、楽になった気がしないという場合もあるのです。
そもそも、人間関係トラブルはどこにでもあるリスクであり「職場の人間関係は悪くて当然」と断言する医師もいるほどです。
そのため、人間関係ストレスを全く感じないという職場を探すのは難しいでしょう。それを目的にしてしまうと、延々と転職を繰り返すことになってしまうかもしれません。
以上を踏まえた上で、転職と現職への残留のどちらが適切なのか、十分に検討する必要があるのです。
2-2. キャリアプランに沿わない転職になってしまう可能性がある
本来、転職とはキャリアアップにつながる前向きな決断であるというのが理想的な形です。そしてそのためには、適切なタイミングで適切な職場へと移ることが大切になります。
しかし、人間関係を理由とした転職では、キャリア上では時期尚早な転職になってしまったり、人間関係トラブルから逃れたいがためにキャリアプランとうまくリンクしない転職先で妥協してしまったりする可能性があります。
そうなると、キャリアがうまく積み重ならないという事態に陥ってしまいます。そのため、転職を決断するまでには慎重に検討を重ねる必要性があるのです。
3. 人間関係を理由とした転職をするか否か判断するための4つのステップ
人間関係が理由の転職をする場合には慎重に検討する必要があるということを理解できたところで、具体的にはどうしたらよいのかを考えていきましょう。
「人間関係を理由に転職するか否か」を判断するためには、以下の4つのステップを踏むことをおすすめします。

まずは、自分のストレスレベルや人間関係トラブルの根本がどのようになっているのかを明らかにします。
次に、人間関係トラブルへの対策を実行し、よい転職先はあるのかリサーチします。
最後に、ストレスレベル・対策を講じたことによる人間関係の変化・転職先情報を材料にして、転職と残留のどちらが満足度が高くなりそうかを検討しましょう。
次の章から、各ステップの詳細について解説していきます。
4.【STEP1】現状を正確に把握する

最初のステップでは、自分のストレスレベルと人間関係トラブルの根本的な原因を明らかにします。
ストレスがあまりに強ければ、一刻も早く転職するか、休職も視野に入れる必要があります。また、人間関係の何がどのように問題なのかを分析すると、対策を講じることで現職に留まれそうか否かがみえてきます。
つまり、転職の必要性と緊急度を判断するために必要なステップなのです。
4-1. 自分のストレスレベルを知る
人間関係トラブルによるストレスの強さは、転職すべきかどうかの重要な判断指標になります。
ストレスはうつ病などの精神疾患のみならず、がんなどの身体的な疾患の罹患率も高めることがわかっています。そのため、強いストレスを感じている場合には、現在の状況を早急に改善する必要があるのです。
まずは、自分は人間関係トラブルに対してどの程度ストレスを感じているのか、許容範囲なのか否かを考えてみましょう。
さらに、以下のようなサイトを利用して得られる客観的な指標も参考にしましょう。
| 職場ストレスチェック | ストレスの度合いと対応の必要性がわかる |
| うつ病チェック | うつ病の傾向がみられるか否かがわかる |
その結果、「気分が落ち込んで何もする気になれない」「眠れない」などのうつ傾向や、「動悸やめまい、胃腸の不調」などの身体症状が出ている、あるいは自分の許容範囲を遥かに超えていてもう耐えられないという場合は、ストレスレベルが重度です。
ストレスレベルが重度の人は、早急に転職または休職に向けて動き出しましょう。
気分が落ち込むことはあるがずっと続くわけではない、身体症状はない、ストレスは感じるがまだ許容範囲だと思えるという場合は、時間的な猶予があります。
この先のステップへと進んで、転職と残留のどちらが適切なのかを慎重に検討しましょう。
4-2. 人間関係トラブルの原因を分析する
人間関係トラブルの原因が明らかになると、対策は可能なのか・有効な対策は何か、ということがみえてきます。効果的な対策を講じることで人間関係トラブルが解決すれば、転職する必要がなくなるかもしれません。
人間関係トラブルの原因を明らかにするためには、以下の流れで分析しましょう。
1.人間関係トラブルの象徴的な場面を詳細に振り返る
2.「なぜそれが起こったか」「なぜ自分は辛いのか」を考える
例:「特定の上司に注意を受けることが多く辛い」ケース
1.人間関係トラブルの象徴的な場面を詳細に振り返る
苦手な上司にランチ休憩前に提出した資料に不備があり、皆の前で「こんな初歩的なミスをするなんてどうなっているんだ」と大声で叱責された。周囲の人たちは見てはいけないという雰囲気で静まり返っていた。
以上のように「誰に」「いつどのように」「何をされたか」「そのときの状況」「周囲の人の反応」を振り返ります。
2.「なぜそれが起こったか」「なぜ自分は辛いのか」を考える
次に「なぜ上司は皆の前で大声で叱責したのか」「なぜ自分はそれを辛いと感じるのか」を考えます。
・休憩前の時間がない状況で資料を確認させられたことに腹を立てていた
・不備の内容が、度々指摘されているミスと同じものだった
・ミスは客観的に考えてごくささやかなものであり、とにかく攻撃しようとしていた
・数人で集まっているところに確認を依頼したため、必然的に皆の前でということになった
・上司をなだめる人がいないため、余計にヒートアップした
・ミスは確かに初歩的なレベルで、自分がそれをやってしまったことが恥ずかしかった
・周囲の人に仕事ができない奴と思われるようで怖かった
・誰も味方してくれないことが悲しかった
ここで注意したいポイントは、冷静に客観的に考えることです。辛さのあまり何でも悪い方に捉えてしまうと、本来なら可能である対策を見落としてしまう可能性があります。
分析の結果みえてきた「なぜ」の部分が、人間関係トラブルの原因にあたります。
例えば上記の例のうち、どう考えても攻撃が目的だという理不尽な原因であれば対策は難しいかもしれませんが、資料の確認を依頼するタイミングと場所が原因であればそれを調整することで同じ事態を避けられる可能性があります。
また、自分自身に向けた対策として、同じミスを繰り返さないようにし、一定水準の仕事はこなせていると自信をもつことで、辛さを和らげることもできるでしょう。
一方で、実は人間関係以外のことが本質的な問題だったというケースもあります。
例:辛さの根本的な原因は人間関係ではなく他のことだった
- 「仕事でわからないことを誰に聞いても教えてもらえない」→「新人教育の体制が整っていない
- 「仕事の成果が評価されない、一部の職員がえこひいきされている」→「会社の評価制度の基準があいまい」
- 「上司の言うことが絶対で威圧的」→「古くから社風が変わらない、若い年代が少ない組織構造」
以上のようなケースでは、辛さの原因は人間関係ではなかったと知ることで仕方がないと受け止めるか、体制の改善に乗り出すかという対策になるでしょう。ただし、職場の風土やシステムにかかわることが多いため、個人の努力では改善が難しいかもしれません。
もし、人間関係トラブルの原因を分析する中で、些細なことにも落ち込みやすいという自分自身の傾向が気になったという方は「メンタルを強くする13の具体的な方法を紹介(思考・習慣・食事)」をご覧いただくことをおすすめします。
5.【STEP2】人間関係の改善策を実行する

2つめのステップでは、人間関係トラブルを改善するための方法を実行します。
改善策の効果があれば、ストレスが軽減して転職が必要なくなるかもしれません。また、どの程度効果があったかということが、転職すべきか否かの判断材料になります。そして、転職するにしても残りの在職期間をなるべく辛くないように過ごすことに役立ちます。
つまり、ストレスコントロールをしつつ転職するか否かの判断材料を集めるために必要なステップなのです。
人間関係の改善策は原因に応じたものを実行すべきあり、何が効果的かはケースによりますが、ここではオールマイティに使える以下の方法をご紹介します。
5-1. 笑顔を絶やさず堂々と振る舞う
まずは、いつも笑顔で堂々と振る舞うことを心掛けましょう。
ストレスの強い環境にいると気分が落ち込んだり、苦手な人と関わるときには緊張してしまうこともあると思います。ですが、暗い表情や怯えた言動は、周囲の人を不快な気持ちにさせたり、より攻撃心を煽ることにつながりかねません。その結果、さらに人間関係が悪化するという危険性があります。
一方で、あまりストレスを感じていないかのように見せることができれば、味方になってくれる人が出てきたり、思ったような反応が得られないことで相手が意地悪を諦めることが期待できるのです。
5-2. 仕事上の人間関係はその場限りのものと割り切る
人間関係自体は変わらなくても、その受け止め方を変えれば随分と気持ちが楽になります。仕事上の人間関係は職場内だけのもので、自分にとって大した価値はないと考えてみましょう。
「うまくいかなくて辛い」は、うまくやりたいという期待が強いために起こる感情です。最初から期待しなければ、こんなものだとフラットに受け止めることができるのです。
職場の人と仲良くする必要はありません。必要なのは「業務を支障なく遂行するために不可欠なやりとり」のみです。逆に、それさえもままならないようであれば、問題はかなり深刻だといえます。
5-3. 苦手な相手ほど報連相を徹底する
苦手な相手とはなるべく関わりたくないと思いますが、業務上必要な報連相はむしろ積極的に行いましょう。
報連相が不十分だと、仕事が滞ったりミスが発生する危険性があります。そのような事態になれば、苦手な相手との間の雰囲気がより悪くなったり、リカバリーのためにそれまで以上に緊密に関わらなければならなくなるかもしれないのです。
また、人は真摯に仕事に取り組む様子やめげずにがんばる姿勢を好ましく思うものです。たとえ冷遇されてもきちんと報連相することで、苦手な相手の態度が軟化する可能性もあります。
5-4. 第三者に相談する
ストレスや悩みは、自分ひとりで抱え込んでいると客観的な判断が難しくなり、辛さが増したり解決策はないと思い込んでしまったりする場合があります。
誰かに話すことで、気持ちが落ち着いたり状況が整理できることがあるため、試してみましょう。
まずは、辛い気持ちを否定せずに話をきいてくれそうな、身近な人に相談することをおすすめします。その際は、相談したことが流出して余計人間関係が悪化することを防ぐために、職場とは関係のない人か、職場の人でもトラブルとは無関係な信頼できる相手を選ぶことが大切です。
もし、人間関係トラブルの内容がいじめやハラスメントであれば、会社や労働組合の相談窓口、もしくは公的な「総合労働相談コーナー」を利用しましょう。
5-5. ストレッサーと距離をおく
可能であれば、ストレスの元になっている人間関係と距離をおきましょう。
仕事に支障のない範囲で、連絡には対面だけではなくメールも活用する・業務の割り振りを変更する・休憩時間をずらすなどによって、ストレッサーとの接点を減らします。
ただし、相手に避けていると受け止められると余計に関係が悪化することがあるため、注意が必要です。こちらから近付くことはしなくても、相手からのコンタクトは受け入れるというスタンスでいるとよいでしょう。
人間関係トラブルが重大であったり、希望が通る可能性がある場合には、異動を願い出るのも効果的です。職場の人間関係を円滑にする方法についてより詳しく知りたい方は「楽になる!職場の人間関係を円滑にする方法8つ【最悪な場合の対処法付き】」をご覧ください。
また、上司との関係でお悩みの方は「上司と合わなくて辛い!上司のタイプ別解決策と心が限界の際の対処法」も参考にしていただければと思います。
6.【STEP3】転職先をリサーチする

3つめのステップでは、よい転職先がありそうかどうかをリサーチします。ここでいう「よい転職先」とは、「現職よりも魅力的な職場」のことです。
人間関係を理由として転職するからには、今よりも人間関係ストレスが低そうな職場を選びたいと考えるのは当然です。
しかし、人間関係ストレスから解放されるなら転職先はどこでもよいというわけにもいきません。自分のキャリアプランに適した職場を選ぶのが理想です。また、給与などの待遇も気になるところでしょう。
人間関係だけではなくその他の条件も踏まえた上で「ここなら転職した方がよい」と思える職場があるのかどうかが、転職すべきか否かの判断材料になります。
つまり、安易な転職によって後悔しないために必要なステップなのです。
6-1. キャリアプランを再確認する
転職を検討するにあたって、どんな仕事をどのように積み重ねていきたいかというキャリアプランを再確認しましょう。
そのキャリアプランに適しているかどうかという視点で、転職先をリサーチします。仕事内容・求められる役割・企業のビジョン・モデルケースなどを確認し、将来的にこうありたいという自分のイメージとマッチする転職先を探すことが大切です。
キャリアプランについて詳しく知りたい方は「キャリアプランとは?作り方から面接での答え方・注意点まで解説」をご覧ください。
6-2. 転職エージェントに相談する
転職先に関する情報収集を効果的に行うためには、転職エージェントの活用がおすすめです。
転職エージェントは、一般市場に公開されていない求人情報をもっていたり、職場の内部事情を把握しています。そのため、転職エージェントに相談することで、より自分に合った転職先をみつけることが可能になるのです。
ここで「まだ転職するかどうか決めていないのに転職エージェントに相談していいの?」という心配は無用です。転職エージェントのアドバイザーは、あなたの置かれている状況やキャリアプランを把握した上で、「今転職すべきかどうか」から一緒に考えてくれます。
以下におすすめの転職エージェントをご紹介するので、参考にしてみてください。
リクルートエージェント

リクルートエージェントは、転職支援実績No.1の転職エージェントです。
業界最大級の非公開求人数を誇るため、希望に合った転職先をみつけられる可能性が高まります。
また、実績豊富なアドバイザーによるサポートが充実しているため「やりたいことがよくわからない」という段階からでも安心して転職活動を始めることができます。
doda
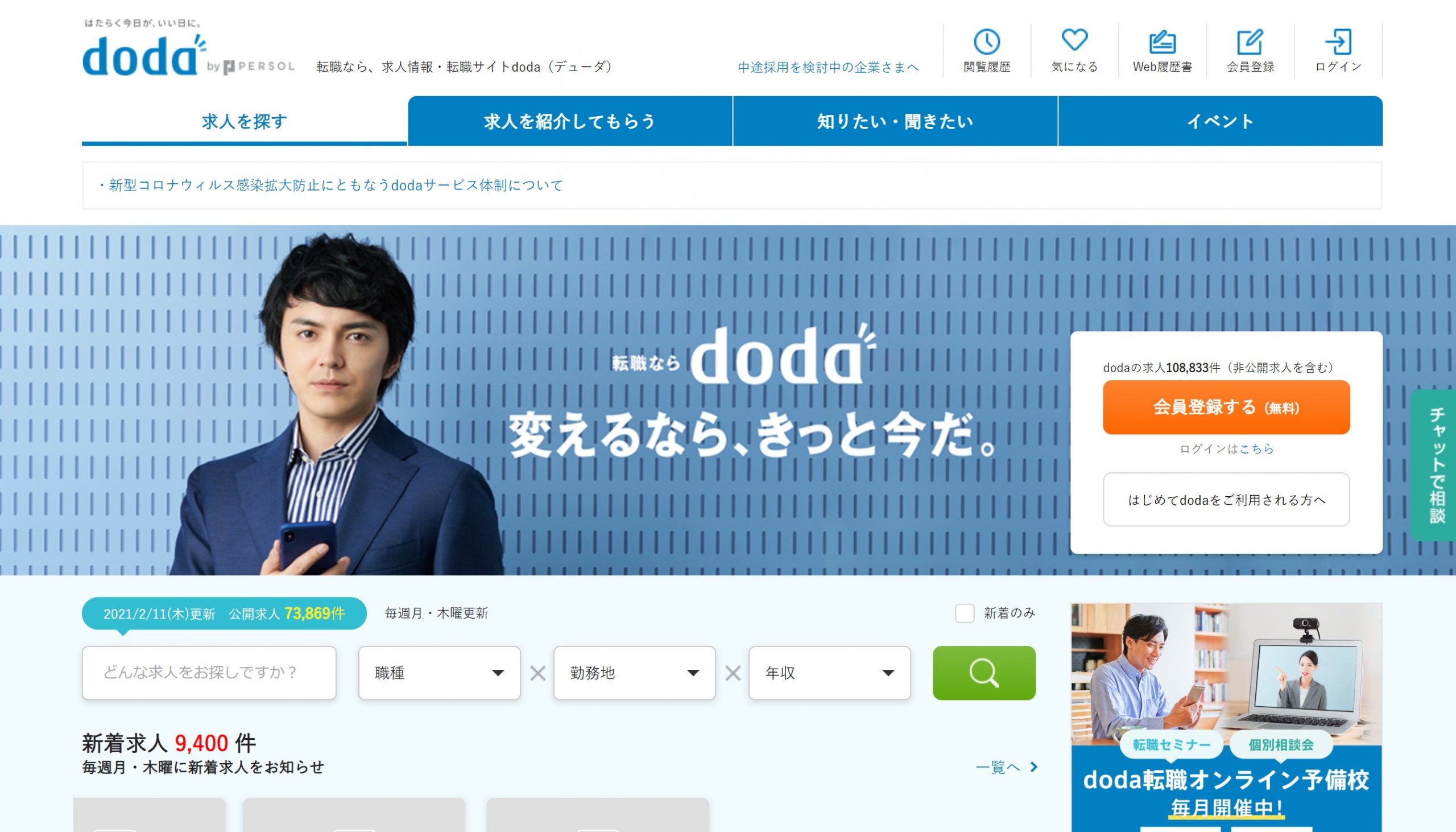
dodaは、転職者満足度No.1を誇る転職エージェントです。
dodaでは求人数・バリエーションともに豊富に揃えているため、こだわり条件にマッチした転職先をみつけられる可能性が高まります。
また、30年間の転職支援実績があるため、ノウハウを熟知したアドバイザーにサポートしてもらえます。
6-3. できるだけ事前に職場見学をする
転職先をリサーチする上では、できるだけ候補の職場を見学しておくことをおすすめします。
職場見学をすることで、その企業での仕事内容や人間関係の雰囲気など、求人情報だけではわからないことがみえてきます。それを「アリ」と感じられるなら、その職場が自分に合っていると判断できます。
職場見学は、ある程度の集団を対象に見学会という形で実施されることもあれば、個別に随時受け付けている企業もあります。まずは気になる企業に問い合わせてみましょう。
また転職エージェントやハローワークが間に入っている場合は、企業とのやりとりを代行してもらえます。
7.【STEP4】転職と残留のどちらが満足度が高いか検討する

最後のステップでは、ここまでのステップで得られた情報を基に、転職と現職への残留のどちらが適切かを検討します。
自分のストレスレベル・人間関係トラブルの根本的な原因・対策を講じた結果・転職先情報を踏まえて、転職と残留のどちらが結果的に満足度が高くなりそうかを推測しましょう。
ここで大切なのは「自分が仕事に関して大切にしたいこと」を明確にし、それを軸に納得がいくまで検討を重ねることです。
つまり、現時点でのベストな選択をし自分がそれを受け入れるために必要なステップなのです。
7-1. 仕事に関して何を優先したいのか整理する
転職と残留どちらにするかの検討を始めるにあたって、まずは「自分が仕事に関して大切にしたいこと」を挙げ、優先順位をつけましょう。
仕事内容、やりがい、人間関係、待遇、ライフスタイルとの親和性など、何は譲れなくてどこまでは妥協可能なのかについて、よく考えてみます。
その結果に照らして、転職と残留のどちらが優先事項を満たすのかという視点で検討を進めましょう。
7-2. 転職と残留それぞれのメリットデメリットを挙げる
転職した場合と残留した場合、それぞれのメリットとデメリットを思いつく限り挙げてみましょう。そしてメリットとデメリットの意味合いを検討します。
「メリットデメリットのどちらが多いか」だけではなく「自分にとって価値の大きいメリットは何か」「どうしても受け入れがたいデメリットはどれか」「相殺できるメリットデメリットはあるか」というように、量と質の両面で考えることが大切です。
7-3. 総合的に考えて満足度が高そうな方を選ぶ
転職と残留それぞれのメリットデメリットを把握できたら、総合的に考えて満足度が高くなりそうなのはどちらなのかを検討しましょう。
例えば「やりたい仕事ができる」ことが最優先事項である場合、残留することで「得意な分野の仕事を任されてやりがいが得られる」というメリットが得られるため転職しない、というのもひとつの考え方です。
しかし、残留のメリットは上記以外になく、ストレスレベルも高い状況だとしたら「同じではなくても似たような仕事内容で、その他の点では現職よりもメリットが大きい」という転職先を選んだ方がいいかもしれません。
転職は多くの可能性を秘めていますが、メリットだらけで迷う余地もないというケースはさほど多くありません。また、人間関係以外にも目を向ける余裕ができたとしたら、残留もデメリットばかりではないかもしれないのです。
そのため、全体的なバランスを考えることが、満足度が高くなるような選択をするためのコツだといえます。
8. 転職先でよい人間関係を築くコツ

十分に検討した結果転職を決断したという場合には、また新しい人間関係を築いていくことが必要になります。
転職先でも人間関係トラブルが起きるという事態を避けるために、よい人間関係を築くコツを押さえておきましょう。
転職先でよい人間関係を築くコツには、以下のようなものがあります。
8-1. 社風を知りそれに合わせる
転職先の企業が何を大切にしているのか・どのような雰囲気をもっているのか・ルールやタブーはどうなっているのかという社風を知り、それに応じた言動を心掛けましょう。
あまりにも社風にそぐわないように見えてしまうと、元からいる人たちから仲間として認めてもらえないことがあります。
社風を知るためには、入職してから観察することの他に、採用担当者や転職エージェントに尋ねてみるという方法もあります。
8-2. 積極的に挨拶や質問をする
関わる人一人ひとりに対して、積極的に挨拶をしましょう。また、仕事に関しては教えてもらうのを待つのではなく、自分から質問をして覚えるようにします。
新しいコミュニティに馴染もうと努力している様子は、好感につながります。その結果、元からいる人たちに受け入れられやすくなるのです。
ただし、プライベートなことをあれこれ質問することは避けましょう。まだ人間関係が出来上がっていない段階では、不快に思われることがあります。
8-3. 求められている役割を確実にこなす
転職先での仕事をなるべく早く覚えて、確実に結果を出せるようにしましょう。
仕事ができて戦力になるとみなされることで、信頼感を得ることができます。一方でどれだけ人柄がよくてもいつまでも仕事が覚えられないとなれば、陰口の対象になってしまうかもしれないのです。
8-4. 率先して貢献する姿勢をみせる
誰かがやらなければならない仕事に名乗り出たり、他の人の手伝いを申し出たりすることで、職場に貢献する意欲が強いことを示しましょう。
人は、自分にメリットをもたらしてくれる相手に好感を抱きやすいものです。「よく働くいい人が来てくれた」と思われることでしょう。
8-5. 前の職場でのやり方を持ち出さない
聞かれてもいないのに「前の職場ではこうだった」と言うのはやめましょう。
元からいる人たちが、自分の職場が劣っていると指摘されたように感じて、反発を受ける危険性があります。
「郷に入れば郷に従え」というように、まずは転職先でのルールややり方に従うのが無難です。改善したいことがあれば、人間関係が安定した段階で提案しましょう。
8-6. 関わる人を観察し特性をつかむ
周囲の人をよく観察し、その人が大切にしていることや嫌だと思うことをつかむようにしましょう。
例えば先回りして資料を準備しておくと喜ぶ人、逐一報告がないと気が済まない人、などの特性を把握して相手がしてほしいことをして嫌がることをしないようにすると、快適に付き合える相手だと思われます。
9. 健やかに働ける環境は自分からつかみにいこう!

人間関係トラブルはどこの職場にもつきものだとはいえ、ただ耐えるという選択をしてしまうとストレスによって病気になってしまうかもしれません。対策が可能であれば、積極的に試してみることをおすすめします。
また、たとえ人間関係が理由でやむなく転職することになったという場合でも、十分な検討の末に決断すれば、キャリアに役立つ有意義な転職にすることも可能です。
脅威から自分を守るのも、最適な居場所を用意するのも、自分自身です。だからこそ、人間関係が辛くて転職が頭をよぎったという時点で、アクションを起こしてほしいと思います。
この記事で解説した4つのステップを活用して「自分の場合は転職すべきか否か」についてじっくり考えてみてください。
10. まとめ
人間関係が理由で転職するのは珍しいことではありません。
ただし、人間関係トラブルはどこにでもあるリスクであり、安易に転職するとキャリアがうまく積み重ならないという事態に陥る可能性もあります。
だからこそ、人間関係を理由として転職する場合には慎重に検討することが不可欠です。
この記事では「人間関係を理由とした転職をするか否か判断するための4つのステップ」の具体的な進め方について、詳しく解説しました。

また、転職を決断した場合に必要な、「転職先でよい人間関係を築くコツ」もご紹介しました。
人間関係トラブルから自分を守るのも、最適な居場所を用意するのも、自分自身です。
健やかに働ける環境をつかむために、この記事がお役に立つことを願います。




コメント